伴鴎亭と黄喜先生遺跡地(반구정과 황희선생유적지)
17.5Km 2024-03-22
キョンギ道パジュ市ムンサン邑パングジョンロ85ボンギル3
伴鴎亭(パングジョン)は、高麗末期と朝鮮初期の文官である黄喜(ファン・ヒ)が領議政(朝鮮時代の最高官職)から辞退し、晩年を過ごした場所で、臨津江(イムジンガン)の下流に建てられた亭です。黄喜先生遺跡地には、黄喜の死後、その死を追悼するために建てられた影堂(ヨンダン)と黄喜の業績についての資料がある景慕斎(キョンモジェ)などがあります。
幸州山城歴史公園(행주산성 역사공원)
17.5Km 2024-02-06
キョンギ道コヤン市トギャン区ヘンジュサンソンロ93-38
幸州山城(ヘンジュサンソン)の隣にある漢江(ハンガン)沿いの公園です。壬辰倭乱(文禄・慶長の役、1592~1598)の期間に朝鮮軍と日本軍の戦闘があった場所でもあります。軍の哨所を再利用した漢江展望台、鉄柵フォトゾーン、風車の丘、芝広場などがあります。幸州山城は歴史ヌリ道コースの1つで夕焼けスポットでもあります。
伴鴎亭ナルトチプ(반구정 나루터집)
17.5Km 2024-02-27
京畿道 坡州市 汶山邑 伴鴎亭路85番キル13
伴鴎亭(パングジョン)ナルトチプは古めかしい韓屋の、長い歴史を誇るウナギ焼きの老舗です。ウナギは韓国人のスタミナ食て、塩焼きにするか甘い醤油ソースをかけて焼いて食べます。肉たっぷりのウナギは炭焼きで、表面はサクサクして中は柔らかいです。火の味がするウナギ焼きと澄んだ豆もやしククがあるおかずのバランスが良く、仕上げですいとん入りのピリ辛ナマズの辛味スープも格別です。
[事後免税店] Olive Young・パジュムンサン(坡州汶山)店(올리브영 파주문산점)
17.6Km 2024-06-27
キョンギ道パジュ市ムンサン邑ムンヒャンロ71 シンソンタワー104号
-
[事後免税店] Olive Young・ウォンフン(元興)駅店(올리브영 원흥역점)
17.8Km 2024-06-27
キョンギ道コヤン市トギャン区クォニュルデロ668ティーオーピークラシック101、102、107、108号
-
江華風物市場(강화 풍물시장)
17.9Km 2021-12-09
仁川広域市 江華郡 江華邑 中央路17-9
在来市場である江華風物市場は、江華民俗場名所化事業により現代化され、2007年に新築されました。市場周辺の空き地や道路沿いにおよそ300ほどの露天市が開かれ、近くには江華人参センターや土産物センターもあり、見どころが多いエリアです。正月テボルム(旧暦1月15日・小正月)の直前頃になると、露天市にはさまざまなナムルや落花生、胡桃などのナッツ類やさまざまな野菜など、ないものはないというほどの品物が並びます。市場の1階にはさまざまな業種の店がある風物場、刺身センターがあり、鮮度のよい刺身を食べることができます。2階は同じくさまざまな店がある風物場や食堂があり、江華島を巡る旅の途中で、あるいは旅の終わりに腹ごしらえをするのにオススメです。2と7のつく日には風物市場を中心に江華邑五日市も開催されます。
江華人参センター(강화 인삼센터)
18.0Km 2021-04-13
仁川広域市 江華郡 江華邑 江華大路335
+82-10-9314-3348
江華の高麗人参は1232年ごろに栽培が始められ、1920年代に特別区域として指定されました。韓国戦争当時、開城で高麗人参を栽培していた人々が避難しながら栽培する場所を探していたところ、江華島の土壌と気候条件が高麗人参の栽培に適していたため、ここで栽培を始めました。これが江華の高麗人参6年根の始まりです。四方を海に囲まれ、海風の影響を受ける気候条件とシルト質粘土の土壌がある江華は、高麗人参の栽培に最適です。農協では肥沃な土壌で育った良質の高麗人参を、生産から加工、流通に至るまで責任をもって消費者に提供しています。
緑青瓷博物館(녹청자박물관)
18.0Km 2024-09-11
仁川広域市 西区 陶窯址路 54
+82-32-560-2932
旧景西洞(キョンソドン)事務所を改築し2002年10月25日に緑青瓷陶窯址資料館を開館しました。国家史跡景西洞緑青瓷陶窯址に関する学術資料の提供および陶磁器体験教室の運営を行っている緑青瓷陶窯址資料館は1965年と1966年に4回にわたる発掘調査を行いました。
この陶窯址で焼かれた瓷器は、精選された青瓷系の薄い胎土(陶磁器の生地の土)の上に調質の緑褐色の釉薬を塗り焼いた緑青瓷器(青磁器)です。景西洞緑青瓷陶窯址は1970年5月、史跡に指定され、地元では初めての文化財となりました。
緑青瓷が生まれた年代については、諸説がありますが、新羅時代末期から高麗時代初期(9世紀から10世紀)ごろ、比較的品質に優れた日暈底青瓷が発達し地方の豪族など富裕階層に普及・広がりを見せる一方、緑青瓷器は高麗時代前期から朝鮮時代後期まで庶民の器として作られたものと見られます。
陶窯址の構造や様式を見ると、丘陵地に西南方向に向かって作られた窯床の長さは7.3m、幅1.05m、焚口の幅1.2mであまり目にすることがない小規模の窯跡です。 窯の傾斜度は22度ほどの単室窯ですが、この窯址で注目されるのは緩やかに傾斜する窯床の表面に土で作った円形のトジミ(ケットク)と呼ばれる焼台を配置している特殊な様式です。 この焼台の形はあたかも馬のひづめのようなの形をしており、前の部分は分厚く、後ろの部分は薄く低めに作られています。登り窯のように傾斜した窯の床の上に焼台の分厚い部分を窯の傾斜の下の方に向けて置くと、器が窯の中で傾かず水平を維持することができます。
このような構造様式の陶窯は日本では独自のものであると自負してきましたが、このような陶窯址が日本のみならず二か所で発見されたため、ここ仁川・景西洞緑青瓷陶窯址の発掘は、今後の研究如何によっては陶窯技術の日本への流出経路を明らかにする貴重な資料となると思われます。
・増築: 2002年9月 27日
幸州山城(행주산성)
18.0Km 2022-11-25
キョンギ道コヤン市トギャン区ヘンジュロ15ボンギル89
徳陽山頂上に築かれた「幸州山城(ヘンジュサンソン/史跡)」は、 壬辰倭乱(文禄・慶長の役)で、日本軍と朝鮮軍がぶつかった激戦地です。
幸州(ヘンジュ)対戦祭
毎年3月14日、幸州山城では壬辰倭乱の時に日本軍を撃破し、国を危機から救って大きな功績をあげた権慄の幸州対戦を記念した行事とその他多彩な文化イベントが開催されます。多くの人達が参加する中、権慄都元帥の掛け軸が奉られている忠壮祠で行われるこの行事は高陽市長が初獻官となり、将軍の魂を呼び起こすための儀式など様々な伝統儀式が行われます。
仁川景西洞 緑青瓷窯址(인천 경서동 녹청자 요지)
18.0Km 2024-09-25
仁川広域市 西区 陶窯址路 54
+82-32-440-4063
1970年5月に史跡に指定され、地元初の国家指定文化財となった仁川・景西洞緑青瓷窯址(インチョン・キョンソドン・ノクチョンジャヨジ)。
1984年12月9日、この場所に遺跡を保護するための広さ82.6平方メートルの保護幕舎が設置しました。ここで発掘された器種は平鉢、大皿などが主で、たらいのような形をした陶磁器・チャベギ、盤口長頸瓶、甕などが出土しました。釉薬の色は緑褐色や暗緑色で不透明で光沢がなく、表面に斑点のようなものがあるものの、これは釉薬の成分、窯の特殊構造、焼成温度などが影響したものとみられます。
斜面を利用した窯は傾斜度22度ほどの単室窯となっています。この窯址で注目すべき点は、緩やかに傾斜した窯床に、土で作った円形のトジミ(ケットク)と呼ばれる焼台を配置しているのが特徴です。
このトジミは、窯に詰めて焼く際、これから焼こうとする陶磁を置く焼台で、器ひとつひとつをその上に置き、器の底が窯床に直接触れないようにするために設けられたものです。
この焼台の形はあたかも馬のひづめのようなの形をしており、前の部分は分厚く、後ろの部分は薄く低めに作られています。
登り窯のように傾斜した窯の床の上に焼台の分厚い部分を窯の傾斜の下の方に向けて置くと、器が窯の中で傾かず水平を維持することができます。つまり、窯床自体は傾斜がありますが、焼台を置くことにより窯の中に置かれた器が水平を保つように調節できるようになっています。そのため窯の下の方へ行けば行くほど焼台の高さが高くなり、その上に置かれた器が傾かないよう焼台の高さを調整しています。
このような構造の陶窯址は以前には日本でのみ2か所発見されていたにすぎなかったことから日本独自のものと思われていましたが、仁川・景西洞緑青甕窯址が発見されたことにより、今後の研究如何によっては陶窯技術の日本への伝達経緯を明らかにする貴重な史料となることが期待されています。
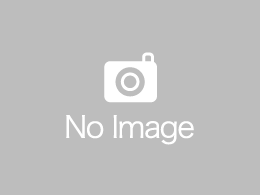







 日本語
日本語
 한국어
한국어 English
English 中文(简体)
中文(简体) Deutsch
Deutsch Français
Français Español
Español Русский
Русский